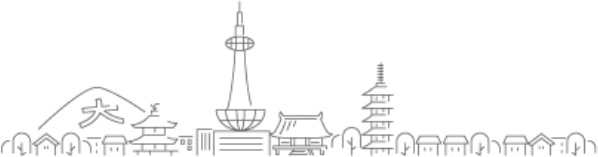2024年度一般会計決算等に反対討論,加藤あい議員(左京区)
2025.10.30
-scaled-e1761817555683-1024x578.jpg)
日本共産党市会議員団は、報第2号一般会計決算、報第4号国民健康保険事業特別会計決算、報第5号介護保険事業特別会計決算、報第6号後期高齢者医療特別会計決算について、認定しないと表明していますので、私は議員団を代表し、その理由を述べ討論いたします。
まず、報第2号についてです。
認定しない第一の理由は、市民生活や子育て・市内中小企業への応援施策が乏しい決算だからです。
松井市長のもとで、初めての通年決算であります。2024年度は58億円の黒字、これで、4年連続の黒字となりました。敬老乗車証の本人負担3倍化や保育園補助金削減など市民生活に多大な負担を押し付ける路線が継続されたことは重大です。新京都戦略で「市民生活第一の徹底」を掲げるのであれば、まずは、傷んだ市民のくらしこそ応援すべきです。動物園や文化施設など191施設の入場料・使用料の値上げ、いきいき市民活動センターの廃止は、「市民の居場所と出番」をつくるという方針とも矛盾しています。
本市の97%を占める中小企業の賃上げ支援について求めましたが、「まずは事業をうまく回して収益をあげて賃上げにつなげよ」との答弁でありました。それができないから、中小企業は困っているのではありませんか。京都府とも連携し、市内の既存中小事業者に賃上げへ直接支援を講じることは、本市として当然の役割であります。
本市の子育て支援は大きく後れを取っています。党議員団が昨年の11月市会に提案した通り、過去負債返済の平準化等で、小中学校給食費の無償化・子ども医療費18歳までゼロができる根拠があったことが示されました。京都市出生率最低更新と報じられました。子どもを産む、産まないは個人の選択であることは言うまでもありませんが、子育ての環境整備は京都市の喫緊の課題です。施策化を強く求めるものであります。
京都府就労・奨学金返済一体型支援事業について、「協議が整えば来年度から制度拡充」と答弁がありました。事業者支援にとどまらず返済している本人も軽減されるような制度が必要です。
そのほかの子ども施策についても申し述べます。
児童相談所の一時保護所のひっ迫について「第三者評価の受診結果」で早期改善提言が出されています。一刻の猶予もありません。体制の抜本的強化と第二児童相談所に一時保護施設を付設することを求めます。学童保育所の大規模化・過密化は子どもたちの「生活の場」の保障からかけ離れています。早急な改善が求められます。20年前の一元化児童館130館目標を見直し、学童保育や児童館の新たな整備方針を策定することを求めます。民間保育園保育士の処遇改善については、国の公定価格の引き上げ分を現場に還元し、削減した補助金は元に戻すべきです。宿舎借り上げの対象拡大を求めます。不登校児童生徒の対策について「多様な子どもを包摂する学校づくり」の表明がありましたが、教職員の採用拡大が必要であることを指摘しておきます。
いずれの施策も、子どもの権利保障・子どもの最善の利益に立った京都市政を求めるものです。
認定しない第二の理由は、国と一体で大型開発行政を推進、公共の民間市場化を進めていることです。
都市再生緊急整備地域の指定で、三条京阪や、京都駅周辺の大改編が進められています。京都駅南側では京都市にあるオフィスの5倍の面積を供給する規制緩和がすでに行われています。東京はじめ全国では駅前開発がとん挫し、高層ビルはどんどん空室が増えています。50年後、100年後においても歴史都市京都が持つ優れた資源を守るために策定されたのが新景観政策であります。この理念に立ち返るべきです。
京都駅新橋上駅舎・自由通路整備は110億円の税金投入ですが、駅前の高層ビル計画と一体のものであり、在来線の減便の一方で1740億円もの経常利益を見込んでいるJR西日本に社会的責任を求めるべきであります。鴨川東岸線第3工区、国道1号線バイパスなど車を呼び込み交通量を増やすのではなく、持続可能性を重視した都市づくり、生活道路の改善を優先すべきです。北陸新幹線京都地下延伸計画については、どのルートも、どの案も混迷しています。与党の枠組みが変わった今こそ、市長が積極的に現行案に市民合意がないことを発言すべきことを指摘しておきます。
農業政策において、「農地を産業用地とする方針はない」との表明がありました。ならば、向島農地を第二期地域未来投資促進基本計画における重点促進区域の指定からはずすべきです。
一方で、深刻化する気候危機対策については、CO2削減目標についても後ろ向きな姿勢が示されました。京都議定書発祥の地である本市こそ危機感を持ち、踏みこんだ削減目標を掲げ取り組むべきです。
観光政策については、今市会で、宿泊施設拡充・誘致方針の廃止が表明されました。遅きに失したと言わなければなりません。観光立国を国とともに進めてきたのが本市ですが、これがオーバーツーリズムを引き起こし、地域住民の生活と安全を脅かす原因となっています。総量規制で住んでよし訪れてよしの京都市をつくることが、質の良い観光を提供することになります。住宅宿泊事業について「条例による規制強化を検討する」との表明があり、また、簡易宿所も含めた「民泊」規制について検討していくと答弁がありました。党議員団が修正提案にしめした立地規制や管理者常駐など実効性ある規制を求めるものです。
多文化共生推進について、差別・排外主義に対し、市長がガバメントスピーチを発し、ヘイトスピーチ規制条例を制定することは多文化共生を推進してきた本市の責務であることを強調しておきます。
認定しない第三の理由は、「公共人材の疲弊」と言いながら処遇改善ではなく、公務の民間委託化・非正規化、職員削減を進めているからです。
決算年度において、会計年度任用職員の雇止が行われました。民間では許されないことが、安定雇用に率先して取り組むべき自治体で行われていること自体が問題です。本市の会計年度任用職員は専門的な業務に多く任用されています。継続性が重要ではありませんか。再度任用の上限撤廃を求めるものです。
男女賃金格差是正について特定事業主として積極的役割を果たすことが必要です。本市の女性の管理職登用は政令市16位にとどまっています。市長からは「女性の登用についてはしっかり前にすすめていかなければならない」と表明がありました。ならば、男女共同参画計画案で同じ指標を現状把握にとどめていることは改めるべきです。能登半島地震は地方自治体の日ごろの体制がいかに重要かを明らかにしました。民間委託化や職員削減の路線そのものを見直す必要があります。
決算年度に復活した「まちの匠・ぷらす」については「グレーゾーンで十分な耐震性能が確保されていないものもありうる」「支援対象を検討中」と答弁がありました。災害に強い街をつくるために積極的な施策化を求めるものです。
市立病院の今後のあり方検討に際し、市長は、国の示した京都・乙訓医療圏の医療需要を検討の根拠とすることを「適切」と述べられました。しかし、この医療需要見込みは、診療実績に将来推計人口をかけたものに過ぎず、必要量ではありません。国の病床削減、機能分化の誘導に従うことでは市民の命に対する責任は果たせません。国言いなりではなく、公立病院として潜在的な医療需要を掘り起こしていく立場に立つことを求めるものであります。
市営住宅については、ストック縮小・市場開放を優先、貴重な市民の財産が削られる一方であります。「住まいは人権」を率先して実現することにこそ市営住宅の役割があります。今回、単身者用住居の空き家公募について、これまで39㎡としてきたものを53㎡まで対象拡大していると説明がありました。にもかかわらず、団地再生計画の単身者住宅は35㎡とあまりにも狭くなっています。最低居住面積を基準にした居室面積で十分としていることは、あまりに不見識です。居住面積を拡大すべきです。また、家賃減免制度を元に戻すべきです。指定管理者制度導入がすすめられていますが、公共が責任を放棄するのではなく、責任を果たす、その中で、コミュニティを再生していくことこそ必要です。
公園についてPark-PFIやPark-UPで民間活用を進めていますが、公園面積の拡大の努力こそ、公共として進めるべきであります。
最後に、報第4号国民健康保険特別会計等について述べます。国民健康保険が「相互扶助なのか」「社会保障なのか」議論となりました。国保法にない「相互扶助」の言葉をもって、行政責任を曖昧にすべきでありません。行政が胸に刻むべきは、国民健康保険は社会保障であり、国民皆保険制度の根幹であるということです。負担の限界を超えた国民健康保険料を引き下げるべきであることから、認定しません。また、報第5号介護保険事業特別会計、報第6号後期高齢者医療特別会計決算はいずれも保険料が値上げされており、被保険者の負担の増大は避けるべきことから、認定しません。以上、申し述べて、私の討論と致します。