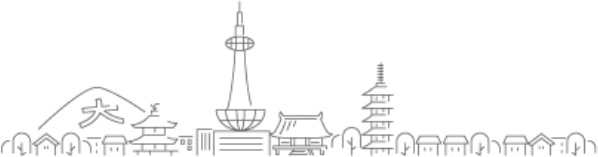「京都市学校給食センター(仮称)整備運営事業実施契約の締結」の条例案に反対討論,玉本なるみ議員(北区)
2025.10.30
-scaled-e1761817381298-1024x577.jpg)
日本共産党市会議員団は議第104号 京都市学校給食センター(仮称)整備運営事業実施契約の締結について反対の立場を表明していますので、私は議員団を代表し、反対理由を述べます。
全員制の中学校給食実施に向けた住民運動は、約30年前から取り組まれ、共産党は当時より議会で取り上げてまいりました。しかし、当時の市長が、「愛情弁当論」を掲げ、2000年に選択制給食が始まり、京都市は選択制給食がベストだという立場で、今まで続けてまいりました。
小学校のような全員制給食の要望が強まる中、教育委員会がおこなったアンケートでは、給食を申し込まず、昼食そのものを食べてない生徒もいることがわかりました。議会には11年間で16回の請願を経て、ついに、教育委員会は2023年1月の議会で全員制の中学校給食に取り組む方針を示しました。あり方検討委員会も発足され、京都市の小学校の自校調理方式が素晴らしいことなども議論されたにもかかわらず、南区の塔南高校跡地を利用して巨大給食センターで48校分22,000食、13校分を民間の調理場2か所で、給食センターと同様の機器や方式で委託するとしています。給食の開始は2028年(R10)年8月の予定ですが、待ちに待った全員制給食だけに、小学校のような出来立てで安全安心で美味しい給食を実現するべきです。
すでに、小中一貫校の7校の中学生は自校調理方式で食べています。さらに、当初の調査では自校方式でできる可能性のある学校は6校、親子方式ではさらに10校あるとされていたことから、実施可能な学校から先行的に実施し、必要な予算を確保し実行していれば、早期に全校実施はできていたはずです。教育委員会の責任は重大です。
以下、巨大給食センターの問題点を5つ述べます。
第1に、学校給食法で努力義務として位置づけられている2時間喫食問題です。市長総括質疑において吉田副市長は「2時間喫食の遵守は極めて重要なファクターである」と認識を示されました。それではいかに、遵守するかが問題ですが、センター方式を実施している多くの自治体で守られていない実態があります。今回の契約事業者と同じ事業者に委託している京都府内の自治体では3年間も保健所から「2時間喫食を守るよう工程を見直すように」指導されているにもかかわらず、改善できていません。他の政令市において、要求水準書には守るように書いておられますが、2時間喫食は守られておらず、やはり、保健所から指導はあるが、改善できていないという状況にあります。つまり、巨大給食センター方式の抱える構造的な問題ではないでしょうか。いくら、配送車が予定時間内に走ったとしても、各献立てが仕上がる時間はバラバラにならざるを得ず、順次食缶に詰める作業にも時間がかかります。ある政令市では、時間がかかる揚げ物で、最初に配送する学校の「調理できあがり時刻」が午前8時28分という場合があるとのことです。その場合、喫食までに3時間42分にもなっています。当然是正するべき時間だと思いますが、改善は難しいとのことでした。つまり、2時間喫食のハードルは高いということです。
第2に、センター給食の場合、良い給食にしようとすると偽装請負になりかねないという問題です。別の政令市の担当者への聞き取り調査では、栄養教諭が調理場に入り、味見をして、その場で調理員に指導もしているとのことでした。調理現場では委託者のチーフを呼び出し、やり取りをするのでは間尺に合わないということです。これでは違法状態と隣り合わせとなってしまいます。
第3に、学校給食で大事な食育教育が不十分だということです。今回の方式で整備すると、栄養教諭の配置は国の基準では3人です。1棟2場方式により倍の6人の栄養教諭の確保を文部科学省に要請し、京都市として独自の加配も行うと答弁では答えていますが、不確定です。給食センター方式を取り入れている他の自治体では、その多くにおいて学校への配置はされていません。学校調理の場合は、小学校のように栄養教諭の配置が可能になります。オンラインを通じてのセンター調理員との交流を行うとの説明もありましたが、大切なのは、日々の給食の中で栄養の大切さなどの専門的な学びと交流ではないでしょうか。以上のこと等により、「学校調理方式に勝るものはない」ということであります。
第4に、PFI手法のBTO方式が京都市にとって、施設整備や今後の運営についての具体的な姿や財政効果が不透明ということです。しかも、1社しか入札しておらず、競争性も働いていません。建設後は公共団体が施設の所有者となるため、京都市が大規模修繕などのリスクを負担します。したがって、BTO方式というのは、民間事業者にとって有利で参画しやすいというふうにされています。動議でも述べた通り、当初147億円とされた施設整備費が220億円に膨張した理由など、今回のPFI契約が適正なものなのかどうかの検討も不十分です。
最後に、整備予定地の問題です。まず、豪雨災害による水害リスクについてです。整備予定地は推定浸水深が3メートルから5メートルというイエローゾーンの立地条件にあります。公共施設を一か所に集中して新設するということは、新たな災害対策とそれに係る費用が増えることは免れないということです。
さらに整備予定地の元東吉祥院公園はスポーツ公園と広域避難所としての存続を求め係争中であります。周辺地域の皆さんにとっては大切な公園であり、裁判の結果によっては整備予定地として使用できないこともあり得ます。今、このような状況にある中で、本議案を可決すべきではありません。
以上、申し述べまして、反対討論を終わります。ありがとうございました。