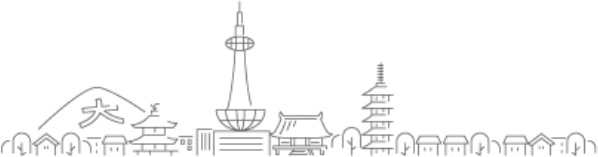山田こうじ議員(右京区)代表質問,消費税,国保料,中小企業,伝統産業
2025.10.02
〈代表質問の大要を紹介します〉
右京区選出の山田こうじです。日本共産党京都市会議員団を代表し質問をします。
1.消費税は廃止をめざし、5%に減税、インボイス廃止を国に求めよ
物価高騰が営業とくらしを直撃しています。参議院選挙では、自民党を除くすべての政党が物価高騰対策として消費税減税を公約し、当選した6割の議員が消費税減税を求めていました。
消費税は生計費非課税の原則に反し、所得の低い人ほど負担が重く逆進性があり、格差と貧困を拡大し、富の再配分という税の本来の役割にも反し、社会保障の財源に最もふさわしくありません。
中小事業者にとっては赤字でも重い負担となるのが消費税です。
右京区の創業86年になる染色工場の事業主からお話を伺いました。最盛期は売り上げ8千万円ありましたが、昨年は1136万円で、所得はマイナス110万円の赤字で所得税は非課税ですが、消費税の納税は202千円。染色関係の事業者はどこも同じような実態です。赤字でも容赦なくかかる消費税は、文字通り営業破壊税であり、伝統産業破壊税です。
1989年から2023年12月までに国民が収めた消費税は539兆円。同じ時期法人3税と高額所得者の所得税、住民税の減税は613兆円。財界が求めた大企業、高額所得者の減税の穴埋めに消えてしまったというのが消費税の正体です。
法人税の減税をめぐり、石破総理大臣は、参議院財政金融委員会で、企業の内部留保に回っただけと指摘されたのに対し、法人税減税は想定した効果をあげられなかったと答弁しています。消費税を減税し行き過ぎた大企業・大金持ち減税を見直し、応能負担の原則で社会保障の財源を確保することが必要です。
GDPの5割以上を占めているのが家計消費です。消費税を増税し、「自立自助・自己責任」だと社会保障を切り捨ててきた結果、家計がやせ細り経済成長が止まっています。他の先進国では家計消費もGDPも直近5年間で15~30%増大しているのに対して、日本だけ個人消費がほぼゼロ成長となっています。
GDPの主役、家計消費を温め、経済成長の好循環で、新たな雇用と消費を生み企業の経済活動にも暮らしにもプラスになり税収にもつながります。
消費税は廃止をめざし、まずは一律5%に減税し、インボイス廃止を国に求めるべきです。いかがですか。
【答弁→財政担当局長】 消費税について、この間国において、税制度の在り方の議論が行われてきたが、地方税財源に影響を及ぼすことが無いよう、地方自治体共同で要望してきた。本市として、消費税の減税を要望することは考えていないが、消費税について議論される場合は、社会保障や財源確保の在り方と共に、慎重に議論されるべきものと認識している。インボイス制度については、軽減税率の実施に当たり、適正な課税を確保するためのものと認識しており、提案のような要望を国に行うことは考えていない。
2.国民健康保険料の値上げ方針は撤回せよ
次に国民健康保険についてお聞きします。
市長は「相互扶助の考え方に基づき、納付金の変動に応じた保険料設定とする」とし、5年間の保険料引き上げを示しました。国民皆保険の根幹が国民健康保険です。物価高騰に苦しむ市民の暮らしを一層追い詰める、国民健康保険の値上げは撤回すべきです。
印刷業を営んでおられる事業者のお話を伺いました。3人を雇用し、売り上げは4100万円で、令和6年の所得は339万円で、今年の国民健康保険料は448千円でした。物価高騰のなか今年の所得は半減し200万円程度の見込みで減免申請を行いましたがなお263千円の保険料です。国保料のほか所得税75千円、住民税13万円、消費税は110万円、税と国保1568千円を支払うと可処分所得は432千円。生活保護基準の最低生活費2人世帯の生活扶助費157万円を下回ります。
高額な国民健康保険料は生存権を脅かしています。国民健康保険の目的は「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とあります。
一般会計の繰り入れを増やす等、あらゆる手立てを尽くし今後5年間の値上げ方針は撤回すべきです。いかがですか。
【答弁→保健福祉局長】 今後も国保制度を安定的に運営するため、一般会計への過度な負担に頼ることのない、制度の仕組みに見合った保険料設定とすることが必要だ。一方で、急激な負担増とならないよう、引き続き、追加の臨時支援を行いながら段階的に保険料の引き上げを行う方針だ。国保は高齢者や低所得者の加入割合が高いなどの構造的な課題があり、国に対して、財政支援の拡充や抜本的な制度改革について引き続き強く要望していく。
3.地元中小企業への賃上げ支援・人材確保支援について
次に、地元中小企業への賃上げと人材確保のための支援についてお聞きします。
従業員数500人未満の中小企業の、2025年春闘妥結状況の第1回集計によると中小企業の賃上げ率は4.3%で大企業の賃上げ率5.38%、大企業と中小企業の賃金格差が拡がっています。
東京商工リサーチによると8月の企業倒産件数は12年振り800件を超え805件となり、人手不足関連倒産は、人件費高騰12件は前年同期の3倍、従業員退職4件、求人難7件と合計23件発生し、8月では初めて20件台を超えています。
2025年版「中小企業白書」では「構造的な人手不足」が強調されています。賃上げを巡る課題では、大企業の労働分配率は23年度に48.2%にまで低下しているのに対し、人手不足による人件費高騰で中小企業の労働分配率は、小規模企業は80.0%と、利益の大半を賃金に注がざるを得ない事態で、賃上げには直接支援が必要です。
京都総評が25歳単身者の、最低生計費調査を2019年4月に実施しています。その結果、男性で178,390円。女性で175,640円という結果となりました。京都総評は今年7月14日、物価高騰の影響を踏まえて、新たに価格調査や20代の当事者による会議を実施し、最低生計費を再試算。その結果を時給換算すると時給1900円が必要となりました。京都府の最低賃金1122円では生活できません。
岩手県では2024年から賃上げ支援を実施し、2025年度についても、1時間あたりの賃金単価を「60円以上」引上げ、賃上げを行う事業主に対して、従業員1人あたり6万円、最大50人分(1事業所あたり最大300万円)を上限として支給するとのことです。奈良県生駒市や群馬県高崎市、大分県や徳島県でも独自に賃上げ支援を実施しています。
京都経済の主役、中小企業で大幅賃上げができるよう京都市として直接賃上げ支援を求めます。
また、中小企業の人材確保の支援としても、奨学金の返済支援が重要です。府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」についてお聞きします。
9月3日に行われた知事・市長のトップミーティングで市長は「利用者の6割が京都市内事業者で周知に協力したい」と発言され、記者会見では「独自の財政支援を検討する」と述べられました。中小企業の人材確保の上で極めて重要な奨学金の返済支援拡充は、わが党も以前から求めており、府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」について、京都市として府の支援に上乗せ支援を行うべきです。いかがですか。
【答弁→産業・文化融合戦略監】 これまでから、市内中小企業に対し、きめ細やかな経営相談や制度融資による資金繰りの下支えに加え、担い手確保や人材育成、販路拡大やデジタル技術の導入等を支援してきた。国や経済団体等に対して、賃上げや物価高騰対策に関する要望・要請も引き続き行う。今後とも、中小・小規模事業者の経営基盤の強化を図るとともに、賃上げを促す施策を国や府と連携して取り組むことで、地域企業の持続的な発展と構造的な賃上げの実現につなげていく。
府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」は、中小企業等の担い手確保や従業員の定着、若者の負担軽減を目的に実施され、効果的な取組である。制度創設時から、導入企業は着実に増加し、市内企業や従業員からも評価をいただいている。先月の府市トップミーティングにおいて、市長が表明したとおり、今後、より多くの企業に本制度を活用いただくため、制度の拡充について、府と協議し、地域企業の担い手確保と若者の負担軽減につながるよう、財政支援を含め検討を進める。
4.伝統産業後継者支援は、金沢市の制度を参考に
次に伝統産業後継者支援についてお聞きします。
京友禅協同組合連合会は毎年、京友禅京小紋生産量調査報告書を作成しています。それによりますと、2024年度の京友禅の総生産量は230,211反で、前年度比6.1%減少し、最盛期の16,524,684反の1.4%にまで減少し大変厳しい現状です。板場友禅の職人さんは「コロナの時より悪い」と嘆いておられました。コロナ前の2019年の総生産量は372,401反で、この6年間だけでも4割近く減少しています。京都の伝統産業が文字通り風前の灯火となっています。長年にわたり育んできた伝統産業がコロナを経て一層深刻な現状です。
特に、高齢化に伴い後継者の育成は待ったなしです。
加賀友禅、九谷焼など国指定の伝統工芸6業種のある金沢市は「金沢の文化の人づくり奨励金」で人材育成のための奨励金を交付しています。「一般研修者」「新規参入研修者」「希少伝統産業後継者」等6事業を実施し、3年間月5万円から12万円奨励金を給付し新規参入を支援しています。
1989年設立された、3年間研修できる金沢卯辰山工芸工房があり、この研修生にも10数名に奨励金が交付されているそうです。また、新規参入研修者奨励金(月10万円3年間)が交付され、親方にも新規参入者への技術伝承者(月6万円3年間)セットで交付され、3年間で576万円を給付しています。
京都には、京都市立芸術大学をはじめ多数の芸術系大学があります。本市として、芸術系大学の卒業生が京都の伝統産業に従事できるよう学生の伝統産業への就労支援が必要です。
金沢市では後継者支援についても1990年度から2024年度で一般研修者279名、希少伝統産業後継者42名、新規参入者53名、合計374名に奨励金を交付しています。2025年度当初予算では1400万円でしたが、組合からの要望で増額補正を検討しているそうです。
京都市伝統産業技術後継者育成制度の支給額は2年間でわずか40万円。2022年の実績は、23件3,926千円。2023年度は20件で3,967千円。これでは、支援しているとは到底言えません。金沢市の一般会計規模は2千億円で京都の約5分の1。単純には比較はできないとしても予算規模からいえば京都では7千万円以上支援が必要です。
京都市伝統産業活性化条例では、「伝統産業製品等の製造、加工等に従事しているものの後継者を育成するために必要な措置を講じなければならない」としています。
京都市でも、新規参入研修者には月10万円3年間の支援と同時に親方にも新規参入研修者奨励金月6万円3年間の給付を実施し後継者育成を行うべきです。いかがですか。
京友禅は数多くの工程を熟練の技術を持った職人さんが携わる工芸品、伝統産業品です。分業で成り立つ工程が失われかねない事態が起こりつつあります。伝統産業を存続させるため、工程ごとの実態調査を行い、工程を維持できる適切な支援が必要です。いかがですか。
【答弁→市長】 伝統産業業界への就職を促進させるため、令和7年度から新たに、採用の意思のある伝統産業事業者と学生をつなぐ伝統産業技術後継者マッチング事業を実施し、就労支援に取り組んでいる。後継者育成について、産業技術研究所で、伝統産業技術後継者育成研修を実施し、技術・技法の継承に取り組み、伝統産業技術後継者育成制度を実施し、累計で1300名を超える方に直接支援を行ってきた。令和7年度から、技術後継者の定着を図るため本制度の予算を増額し、従事期間や基本給の上限といった対象要件を拡大する見直しを行っている。工程ごとの実態調査と支援について、職員が日ごろから各組合や事業者に出向いて、直接声をお聞きし、業界の実態を把握するとともに、資金不足により老朽化した設備を更新できない事業者に対し、設備改修等補助金を支給するなど、工程の維持に向けた支援も実施している。伝統産業がより身近な存在となるよう、特に未来の使い手、担い手となる児童や若者にその素晴らしさを直に体験する機会を創出すること、学校卒業後も京都に残っていただいて、一人でも多くの若者が伝統産業に関わってくれるような環境をつくることが重要と考えている。今後とも、わが国の誇りである京都の伝統産業の魅力を発信し、技術の継承・発展及び後継者育成に取り組んでいく。
5.農業用地の産業用地化は撤回し、家族農業の振興を
次に、農業について質問します。
コロナ禍による需要減少、ロシア・ウクライナ戦争による世界的な食糧高騰、歴史的な円安による輸入資材・食料の高騰で、食料自給率が38%となっている日本の食と農は、危機的な状況にあります。
昨年の夏、スーパーやお米屋さんの店頭からコメが消え「令和の米騒動」が起こり、政府は「新米が出回れば落ち着く」と、備蓄米の放出を拒み続け、今年3月にようやく入札で、5月からは随意契約で放出を行いましたが、備蓄米だけではコメの需要を賄えず、コメの高騰の根本的解決にはなりません。
政府は米増産へ舵を切りました。ところが京都市は、「地域未来投資促進法」に基づき農地の産業用地への転用を進めています。向島の優良農地に物流センターを呼び込み10haの農地が失われました。らくなん進都の農地を奨励金を交付し産業用地にしようとしています。
農地を産業用地に転換するのではなく農業が続けられる支援が必要です。農地の産業用地化は撤回し、農業振興に転換すべきです。いかがですか。
国際的に評価されているのが「小規模・家族農業」です。従来の大規模化・法人化一辺倒から小規模家族農業を農政の主役にし、生産性指標をもとに短期的な効率性を追い求めるのではなく、地域資源の有効活用と循環、生態系の保護・保存をすすめることで日本の農業を再生しようと農民運動全国連合会は呼びかけています。
千葉県いすみ市では「いすみ市有機農業実施計画」で支援しています。人口3万6千人の農業・漁業が基幹産業の自治体です。小学校9校、中学校3校で2015年から児童生徒2200人の学校給食に地元産の有機・無農薬米の使用がスタートし、2017年秋からは100%有機米に切り替えました。
いすみ市で有機米づくりが始まったのは2013年で、それ以前は有機農業とは、ほとんど縁のない地域でした。そこでゼロから有機米づくりに取り組み、有機農業を目指す県外からの若い転入者が増え、有機米づくりに新たに農家が加わり、わずか4年で学校給食の全量有機米使用(42トン)を達成し、現在はさらに35ヘクタールで120トンを生産するまでに成長しています。
【答弁→木の文化・森林政策監】 農業振興について、まず、本市の南部地域では、水稲をはじめ、六次産業化のモデルとなっている九条ネギや農福連携による京オクラの生産など、消費地に近い利点を生かした農業が展開されている。産業用地創出の取組の中で、農地が対象となるケースはあるが、本市として農地の産業用地化の方針はなく、農業の継続を希望される方には、引き続き支援を行う。
6.所得補償・価格保障で農業振興を、京北地域の活性化を
農業を振興し地域活性化を進めるうえで京北地域の振興が必要です。
右京区の京北地域は豊かな自然が広がり、農業・林業が基幹産業です。京北地域にはIターンで多くの子育て世代の新規就農者がおられます。京北地域の農地は481.8ha、農家戸数は1012戸、うち専業農家は216戸です。2012年から2025年の京北地域での新規就農者は30人でした。人口減少が進む京北地域でこそ、定住人口を増やすうえで農業振興に取り組むべきです。こうした方々が安心して営農が続けられるよう価格保障を国に求め、市として独自の所得補償制度・価格保障制度を検討し、新規就農者の支援を求めます。
また、京北地域には京都市立京都京北小中学校、3か所の保育園、京北病院等があります。公共施設の給食の食材を適正な価格で買い上げ、支援することを求めます。
【答弁→木の文化・森林政策監】 京北地域の活性化には、農業の振興が重要であると考えている。平成24年度以降、新規就農支援に取り組んでおり、京北地域には、23名が就農、定着しているが、うち13名は京北地域に魅力を感じて来られた移住者。農業者にとって重要な販路である直売所「道の駅ウッディー京北」の運営をはじめ、京北米のブランド化やライスセンターの整備支援、「京のグリーン農業推進事業」にも取り組んでおり、今後とも京北・左京山間部農林業振興センターを拠点に、京北地域の基幹産業である農業と林業の振興に取り組む。
7.京北の医療体制確保のためにも、京北病院の存続・改善を
次に、京北病院についてお聞きします。
京北地域にとってなくてはならないのが京北病院です。「京北病院が果たす機能の在り方検討会」の報告書が取りまとめられました。病床機能についてはすべてを地域包括ケア病床に転換し、診療所は廃止し、介護老人保健施設は特別養護老人ホームなど他の入所施設と重なると廃止の方向が示されています。
京北病院の職員からお話を伺いました。地域包括ケア病床は、複数点滴や酸素吸入など高い医療が求められ、1日約3000点、約3万円の診療報酬があります。地域包括ケア病床は維持したかったが、常勤医師がたった2人となっており酸素吸入や複数の点滴管理などの医療を必要とする人の受け入れができずに、今年6月に10床を返上し全38床を看護度の低い急性期病床に変更せざるを得なかったと聞きました。地域包括ケア病床を10床開始するときは、4人部屋を3人部屋にして地域包括ケア病床の面積要件をクリアしたとのことでした。38床を地域包括ケア病床にすべて転換するには医師・看護師など体制を確保しなければ実現できないということです。今求められているのは病床を稼働するための医師・看護師などの体制を確保することです。
また、老健施設は廃止の方針ですが、現在も胃ろう・痰吸引など必要となる利用者がおられます。検討会報告書には、「医療的ケアが必要となる入所者の対応を個別に検討する」とされ、京北から出ていかざるを得ないということです。
地域の方々が「京北の医療を考える会」を立ち上げ昨年末、全戸にアンケートを配布し、400通を超える回答が寄せられ関心の高さが示されました。在り方検討会委員にも届けられ、第3回検討会では委員から「診療所の廃止は違和感がある」「オンライン診療では質が落ちる」などといった意見もありました。高齢化がすすみ、美山からの救急も増える等、医療需要はあるにもかかわらず、救急搬送を受け入れられず、市立病院などへ送らざるを得ない状況です。救急搬送される患者を受け入れるには常勤医師を確保することが必要です。老健施設及び診療所は維持するべきです。老朽化した施設の改築も並行しての検討が必要です。いかがですか。
そもそも、国の医療費削減計画のもと多くの病院の経営が深刻な事態となっています。日本病院会、全国自治体病院協議会など6団体が2024年度診療報酬改定後の病院の経営状況の緊急調査結果を発表し、このままでは「ある日突然病院が無くなります」「地域医療はもう崩壊寸前です」と緊急声明を発表しました。8月6日、公立病院などでつくる全国自治体病院協議会は、2024年度決算で各地の病院の86%が経常赤字だったとの調査結果を発表しました。京都市立病院も極めて厳しい状況です。協議会は「危機的状況」と訴えており、診療報酬の引き上げや地方交付税の拡充などを求めています。公立病院の診療報酬の引き上げや地方交付税の拡充を国に求めるとともに、京都市としても現場の実態、声を聞き現場の求めに応える支援を求めます。いかがですか。
【答弁→吉田副市長】 京北病院は、市立病院からの医師等の派遣や他の医療機関からの応援により、医療提供体制を適切に確保している。人口減少に伴う患者数の減や建物の老朽化等の課題がある中、京北地域への安心・安全な医療の提供と、京北病院の持続可能な運営の両立を目指し、機能の在り方を検討している。病院職員へのヒアリングを行い、地域の方への説明やチラシの全戸配布などにより、丁寧に検討状況をお知らせしてきた。外部の有識者や地元の代表者等からなる「京北病院が果たす機能の在り方検討会」では、病院の入院、外来及び緊急の機能は維持しつつも、診療所は、京北病院に集約・廃止し、老健施設は、地域の介護施設と連携、役割分担が適当とされている。建物についても、老朽化等を踏まえ再整備も並行して検討することが求められている。公立病院を含めた医療機関の経営の厳しさについては、関係団体等からも聞いており、診療報酬の引上げや地方交付税措置の拡充を、これまでから国に対し繰り返し要望している。現場の皆様の声を聞きながら取り組んでいく。
8.戦後・被爆80年の今年、核兵器禁止条約批准を日本政府に求めよ
最後に平和行政について伺います。今年は戦後80年、被爆80年の節目の年となりました。
1945年8月6日、ヒロシマに。8月9日、ナガサキに原子爆弾が投下され21万人の命が奪われ、80年たった今も9万人を超える被爆者が原爆の後遺症に苦しみ続けられています。
以来、被爆者は思い出したくもないつらい被爆体験を「ほかの誰にも味わわせたくない」と語り続け、「核タブー」が核保有国の手を縛り、80年間核兵器は使われていません。
被爆者の運動が国際社会を動かし、核兵器禁止条約が国連で2017年採択され、2021年に発効しています。残念なことに日本政府はアメリカの核の傘にしがみつき核兵器禁止条約を批准していません。
昨年12月、日本原水爆被害者団体協議会はノーベル平和賞を受賞しました。受賞に当たり日本被団協の代表委員の田中熙巳さんはスピーチで、「この運動は『核タブー』の形成に大きな役割を果たしたことは間違いないでしょう」として「市民の犠牲に加えて『核タブー』が壊されようとしていることに限りない口惜しさと憤りを覚えます」と訴えられました。
広島市の平和記念式典で湯﨑英彦広島県知事は抑止力はフィクションだと厳しく批判し「もし核による抑止が、破られて核戦争になれば、人類も地球も再生不能な惨禍に見舞われます。国土も国民も復興不能な結末が有りうる安全保障に、どんな意味があるのでしょう」と断じました。
京都市会は1983年3月23日、非核・平和都市宣言を発しました。
この非核・平和都市宣言の精神に基づき、市長は、戦後、被爆80年の今こそ、被爆者の思いを重く受け止めるべきではありませんか。認識はいかがですか。被爆者の願いを重く受けとめ、市長は日本政府に対し核兵器禁止条約を批准するよう求めるべきです。
私の信条は平和でこそ商売繁盛です。そのために全力を尽くすことを述べ質問を終わります。
【答弁→総合企画局長】 核兵器禁止条約について、これまでから、本市も加盟する平和首長会議において、国に対し、核兵器廃絶に力を尽くすとともに、条約に署名・批准するよう、強く、要請している。国においても、各国で隔たりがある中、核兵器のない世界の実現に向け、対話を通じた現実的な取組を粘り強く進めている。世界恒久平和の実現には、国の取組と同時に、自治体の取組や、市民同士等の交流等も大きな役割を果たす。本市でも戦後80年、被爆80年の節目の年に、被爆の実相等に関するポスター展や、姉妹都市等との交流事業などに加え、市民しんぶんに特集記事の掲載等を行った。終戦記念日には、世界平和の実現と人々の幸福の追求に向けて、更なる努力を行うことを決意する市長のコメントを発出した。今後とも、市民とともに世界恒久平和の実現のため取り組んでいく。