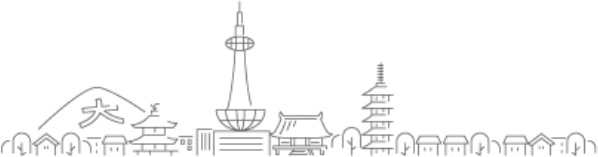選択的夫婦別姓制度の導入を,意見書について討論,やまね議員
2025.03.25
-1024x683.jpg)
日本共産党京都市会議員団は、公明党議員団提案の「選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書」に賛成するとともに、共産党議員団として「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を求める意見書」を提案していますので、以下、その理由を述べます。
まず今回、京都市会には「選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を求め意見書提出を」と求める請願が提出され、3月17日の文教はぐくみ委員会で審査が行われました。そうした経過の中で、複数の会派が意見書を提案していることは、市民の声が議会を動かしていることの表れであることを述べたいと思います。
次に、本市会においては、2021年3月に「選択的夫婦別氏(別姓)制度に関する国民的議論を求める意見書」ならびに「選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書」をいずれも「賛成多数」で可決しております。そのもとで今回改めて意見書を提案することの意義についてですが、今回の意見書はいずれも「法制化に向けた議論の促進」や「制度化」を求めており、さらに一歩進める内容となっている点が重要と考えます。
また、京都市会での意見書可決後も、各種世論調査で、選択的夫婦別姓制度導入への賛成意見が多数となっています。2022年の連合による調査でも、2023年の東京大学と朝日新聞による調査でも、60%以上が同制度に賛成しています。2023年の国立社会保障・人口問題研究所の調査では、60歳未満で「夫・妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」と回答した割合が、単身女性(未婚)で85.3%、離別女性で78.5%、有配偶女性で71.4%、単身男性(未婚)でも61%となっています。
さらに、昨年6月には、日本経済団体連合会が「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」を発表。「人口の半分を占める女性のエンパワーメントにおいて、我が国は世界に大きく立ち遅れており、取組の加速化が急務である」こと、「各社の取り組みだけでは解決できない」「社会制度の課題」があり、「その一つとして見直しが求められている」のが、「夫婦同氏制度(民法第750条)」と訴えています。加えて、昨年10月には、国連の女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓制度の導入について4度目となる勧告も出されています。
請願審査では京都市当局から、「最近では結婚の際に夫の氏を名乗る女性が94.5%」であること、「苗字、姓を変えた人の、52.1%が何らかの不便・不利益があると思うと答えた」との答弁もありました。こうした事態は一刻も早く解消されなければなりません。今回の意見書は、そうした国民世論、経済界、国際社会からの要請に応え、「法制化に向けた議論、国会審議」をより一層進めるものであると考えます。
次に、「通称使用の拡大」では根本的解決にならない点についてです。国際的にはテロ対策やマネーロンダリング対策が強まり、国内外の金融機関の多くは通称での口座開設やクレジットカード作成ができません。通称では不動産登記もできません。契約書のサインもビジネスネームでは認められないことがあります。パスポートに旧姓併記ができるようになりましたが、ICチップには戸籍名しか記録されておらず、入国審査などでトラブルになるケースもあると言われています。
経団連の文書では次のように指摘しています。「通称使用は日本独自の制度であることから、海外では理解されづらく、寧ろダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要するなど、トラブルの種になることもある」「ビジネスの現場においても、女性活躍が進めば進むほど、通称使用による弊害が顕在化するようになった」「これらのトラブルは、これまでは当事者が自身のキャリアを築いていく上での障壁とみなされていたが」「企業にとっても、ビジネス上のリスクとなり得る事象であり、企業経営の視点からも無視できない重大な課題である」との指摘です。
問題は、ビジネス上の観点だけに止まりません。昨年6月、日本弁護士連合会の決議では、次のように指摘しています。「通称使用は、通称名と戸籍名との同一性の証明を要する上に、その二つの名前の使い分けは、本人にとっても他者から見ても煩雑であり、むしろ混乱を招くことにつながっている」「同一性の証明には、住民票や戸籍謄本、複数の証明書等の提出を求められるなど、本来であれば不要な個人情報の開示を余儀なくされ、それ自体が精神的苦痛を伴うものである。また、通称使用は、戸籍姓に準じるものとして扱われるにすぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動ができない精神的苦痛も継続する」。さらにそれらの苦痛は、「結局のところ夫婦の一方のみが負うものであり、通称使用の拡大は両性の本質的平等から遠のく結果にもなっている」との指摘です。通称使用を拡大しても、根本解決にはならず、婚姻により姓の変更を強制される多数の女性が現に被っている人権侵害が解消されるわけではないのです。そもそも、通称使用を拡大しなければならなくなっていることそのものが、夫婦同姓義務付けの不合理性を認めることにほかならないのではないでしょうか。
なお、公明党提案の意見書には、「家族ごとの戸籍制度を守りつつ」との文言がありますが、そもそも夫婦同姓の強制が、戦前の家父長制にもとづく家制度の名残であり、「戸籍制度そのものをなくすべき」とのご意見もあります。同時に、3月12日の衆議院法務委員会では、法務大臣が、「選択的夫婦別姓制度を導入しても」「戸籍制度に大きな影響が生じるものではない」と明確に答弁しており、制度導入が大きな問題を生じさせるものではないことは政府も認めています。
先に紹介した経団連の文書では、「結婚というライフイベントを経ても、本人が望めば自らがアイデンティティを感じる姓を選択できるように社会制度を見直すことは」「性別に関係なくすべての人が自らキャリアやアイデンティティを守る観点からも、大切な取り組みである」と述べています。選択的夫婦別姓制度は、結婚前の姓を名乗り続けたいカップルが選べるようにする制度であり、同姓を希望する人には影響せず、対立するものではありません。今こそ個人の尊厳が守られる社会をつくろう、このことを同僚議員のみなさんに心から呼び掛け、賛成討論と致します。