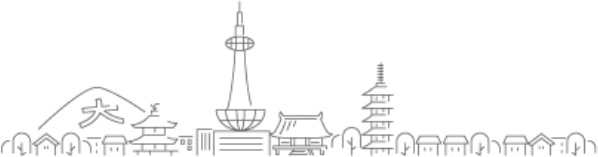山本陽子議員(山科区)代表質問,ジェンダー,観光政策,山科交通
-scaled-e1759471484766.jpg)
<代表質問の大要を紹介します>
山科区選出の山本陽子です。日本共産党市会議員団を代表して市長に質問します。
7月の参議院選挙では、生きづらさを抱える国民の怒りが噴出しました。「外国人が優遇されている」というデマを持ち込み、「日本人ファースト」と掲げた政党が台頭しましたが、差別や分断を招く政治が、生きづらさを解決する救いにならないことは明らかです。
変えるべきは、大企業や富裕層優遇で貧困格差を拡大し、アメリカ言いなりの軍事拡大を進めている自民党政治であり、物価高を上回る賃金の実現や、消費税の減免、医療や福祉の充実で、誰もが安心して生きていける政治に転換すべきです。
そこで、まず、昨年10月の代表質問に引き続き、生きづらさの要因である男女の賃金格差の是正や非正規雇用である会計年度任用職員の問題について、ジェンダー平等の推進を求めて質問します。
1.男女賃金格差解消、育休・時短勤務による女性の不利益解決を
男女平等は昔に比べれば進んだものと思っていても、いまだ家父長的制度の影響で、社会構造に顕著な差異が存在することに私たちは危機感と問題意識を持たなければなりません。特に男女の賃金格差は、女性の低賃金、低年金につながる生きづらさの社会的要因であり、この要因を取り除かないかぎり多くの女性の生きづらさの解消は実現できないからです。
令和5年度から「職員の給与の男女の差異」の公表が大規模事業者に義務付けられました。日本共産党が求めてきたことです。京都市役所職員の数値をみると、女性の給与について正規職員では、昨年男性給与の83.6%であったのが今年は84.1%へ。非正規職員では75.5%から79.1%へと若干の改善が見られました。しかし、男女同等の給与には程遠く、依然として看過できない格差が存在します。
総務消防委員会で給与の男女の差異について質疑したところ、その要因である3つの課題の一つに「柔軟な働き方の推進により女性職員の時短勤務利用が増加している」ことがあげられました。すなわち、柔軟な働き方を推進し、女性が長期に育児休業や時短勤務を選択すると、育休手当はあっても給与収入がなくなるので給与の格差が生じ、さらにそれが老後の年金の減額につながり、経済的な不利益を被る結果になってしまうという致命的な矛盾が生じることが分かりました。これでは、男女の賃金格差は埋まるはずがありません。女性が低年金で、老後の暮らしが厳しい生活の実情をたくさん聞いてきました。育休や時短勤務で女性が経済的不利益を被らないよう国へ対策を求めていただきたいと思いますが、いかがですか。
【答弁→文化市民局長】 男女共同参画社会の実現のため、男女間賃金格差の改善は重要と認識。時短勤務や育児休業による給与減額については、年金受給額に影響しないよう国の特例措置として、標準報酬月額が時短勤務以前の水準として扱われる。今年4月からは、両親ともに育児休業を取得した場合、育児休業給付金に出生後休業支援給付金が上乗せされる。「京都ウィメンズベース」を拠点として正規就労を目指す女性への能力開発や就労支援、仕事と子育て両立支援、女性管理職登用促進などにオール京都で取り組んでいる。今後も、セミナー、情報発信をおこなう。第6次男女共同参画計画でもウェルビーイングな社会の実現をめざす。
2.会計年度任用職員の雇用継続を
二つ目に、公務の非正規雇用である会計年度任用職員の継続雇用を求めてお伺いします。会計年度任用職員は一会計年度の期限付き任用であるところ、京都市では一年ごとに客観的な能力実証を行い4回までの再任用更新を認めています。しかし、5年目には雇止めをして、改めて採用試験を受ける公募を行うとし、昨年実施されました。公務職場で働き続けたいと思っても、5年目に雇止めされ採用試験を受けなければなりません。
会計年度任用職員の皆さんにとって、5年ごとに職を奪われる生活不安はいかほどか。京都市職員労働組合が2023年に行った会計年度任用職員へのアンケート調査では、生計を支えるのは自分と答えた方が48%、自分を含む複数と答えた方が22%でした。自分が職を失えば生計を維持できない方が70%を占めることになります。昨年は500人以上の職員を雇止めし、不安な思いをさせました。また、アンケート調査では公募を行うことのデメリットについて聞いています。雇止めで「これまでの経験が無駄になる」「仕事に対するモチベーションが下がる」「市民サービス低下につながる」「市民との信頼関係が失われる」など、職務遂行に影響のある内容もデメリットだとされていたことは重大です。5年ごとの雇止めが、雇用の安定を害し、また職務遂行上のデメリットを生じさせるものであるとの職員の評価について、正面から受け止めるべきです。
そもそも、労働法に明記された労働条件決定の大原則は「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない」とされています。ここから導かれる雇用の安定は、憲法25条の生存権に基づくもので、軽視していいものではありません。
2013年の法改正により、民間企業では5年の継続雇用で無期契約に転換できる権利を有するようになりました。また昨年は、人事院の通達により再度任用の上限回数が撤廃され、自治体の判断で公募を中止することができるようになりました。その後、公募を廃止し雇用を継続する自治体は増えています。
会計年度任用職員の皆さんの雇用を継続し、安心して働き続けられるよう、5年での雇い止め・公募は廃止し、公務が率先して賃上げや雇用の安定を図るべきと考えますがいかがですか。
「コストカット型経済」で、人件費を削減するために非正規雇用を拡大させてきたことが、貧困の大きな要因となってきました。京都市の会計年度任用職員の平均年収が378万円であるのに対し、正規職員の平均年収は677万円、この格差は重大です。会計年度任用職員は正規職員に転換するよう強く求めます。
【答弁→監察監】 地方公務員法では、会計年度任用職員は一会計年度ごとに任用するとされており、労働契約法における無期労働契約への転換は適用されないことになっている。昨年、国において公募を経ない再度任用の取り扱いが見直されたことは承知しているが、あくまで例外の取り扱いとされており、地方公務員法における平等取り扱いの原則や成績主義に基づく公募が原則であることに変わりはない。京都市では5年に1回の定期的な公募を適切に運用している。勤務条件についても地方公務員法の諸原則に基づき決定している。給与水準引き上げや勤勉手当支給など改善している。
3.子ども医療費助成拡充、給食費無償化の早期実施を
次に、子育て支援の前進について質問します。
昨年10月の私の代表質問では、京都市が行った「家族や家庭生活のあり方に関する意識調査」で、少子化対策として市民が一番求めているのは「子育てにかかる費用の負担軽減」であることを示し、その具体化を求めました。
さらに12月には、日本共産党市会議員団として、子どもの医療費18歳までの無料化や、小中学校給食費の無償化について、50億円すなわち一般財源の約0.5%で実施可能であることを示し、子育て支援無償化条例を提案しました。残念ながら条例は否決されましたが、条例提案をきっかけとして、小中学校の給食費の無償化について「市長の今任期中に...無償化の道筋をつけることができるよう」求める京都市会決議が、全会派一致で採択されました。京都市政にとっての課題の重要性を示しています。
物価高を上回る賃上げがいまだ実現しない中で、子育てにかかる費用の経済的な負担は日増しに生活にのしかかっています。この大変さを京都市は切実に受け止めて、迅速に対策しようとしているのでしょうか。市民が求め京都市会も求めた子育てにかかる経済的な負担軽減として、子どもの医療費助成制度の18歳までの拡充や、小中学校給食費の無償化について、京都市として早期に進めるよう求めます。いかがですか。
【答弁→吉田副市長】 4月から第2子以降の保育料無償化実施するなど、子育てへの経済的負担軽減は重要と認識。国において一律に実施すべきであり要望している。子ども医療費支給制度の拡充は府市協調で取り組む。まずは中学生の通院医療費の制度拡充をすすめる。学校給食無償化については、就学援助世帯の給食費を公費負担、令和4年度以降、食材費の価格高騰分の経済負担軽減をはかっている。国が令和8年度からの小学校給食無償化方針を示しており、対応を検討する。
4.子どもの権利実現へ、球技のできる公園の増設を
さらに求めたいのは、子ども達がのびのびと球技等ができる身近な公園を増やすことです。
子どもの権利条約の実践としても、子どもの声に耳を傾け施策に反映すべきことが、新たな視座を与えてくれます。子ども達の大きな要求は、のびのびボール遊びができる公園やスケートボードができる広場を近くに作って欲しいという、広場の環境整備であるとたくさんの声を聞いてきました。私は3年前にも、東京都豊島区で、住宅地の一角にフェンスを設置して街中でもサッカーや野球が練習できる「キャッチボール広場」が設置されていることを示し、「京都市でも実現を」と求めてきました。当時、行財政改革の真っただ中、相当の費用が必要で困難との答弁でありました。しかし、京都市が指定する球技広場は市内に19か所しかなく、山科区はじめ北区・下京区・東山区には一つもありません。周辺住民の合意や、面積1200㎡以上、4mのフェンス設置という現在の規準がハードルとなり、子ども達の権利実現に消極的になっていると感じます。少し狭くても、今ある環境を活用できないか、住民合意をサポートして球技できるようにできないか、子ども達の願いを受け止め工夫することはできないのか、認識をお伺いします。いかがですか。
昼間は小さい子ども達が遊んでいるので、夜間の公園でサッカーなどしている中高生もいます。球技できる公園がなくて、道路でボール遊びをする子ども達もみかけます。小学生は子どもだけで遊びに行くのは小学校区内の範囲というルールです。球技できる身近な公園の要望は大きいということを受け止めていただきたいと思います。8月に開かれた京都府子ども議会でも、子ども達から「ボール遊び場の拡充」が提案され、西脇知事は「ボール遊びができる時間帯を拡充し、フェンスも設置したい」と応じたことが報道されました。
京都市では、ミータス山科-醍醐の一環として、これから東野公園の整備が行われ、醍醐石田では新たな公園が整備されることになり、議会で重要性を議論してきた成果と感じています。さらに踏み込んで子ども達の願いを受け止めて、小学校区に一つ以上、球技ができる公園を増やしていただきたい。いかがですか。
まず、ここまでの答弁を求めます。
【答弁→市長】 新京都戦略で、未来を担う子ども、若者を社会全体でともにはぐくむことを政策の柱に掲げた。多様な経験ができる場が不可欠であり、公園は子どもの居場所となる。誰もが気楽につどえるパブリックテラスのような公共空間づくりに取り組む。球技のできる公園は、ParkーUP事業で独自のルールを設けることが可能。社会実験を予定している公園もある。市民のご意見をしっかり受け止める。
【山本議員】 球技のできる公園の増設については、育ち盛りの子どもたちを喜ばせるような実績をぜひつくっていただきたいと思います。
会計年度任用職員については、7割が女性職員です。重要な公務の担い手といいながら、不安定で低賃金の非正規雇用に押し込める市政は問題です。男女の賃金格差の問題も、女性の活躍といいながら格差是正についてはあまりにも弱腰でした。引き続き遅れている京都市のジェンダー平等の推進を求めていきます。
5.「宿泊施設拡充・誘致方針」の廃止、観光政策の転換を
次に観光政策についてお伺いします。
この間、市民からは、観光客の激増で生活への悪影響が生じるオーバーツーリズムは何とかしてほしいという声を聞いてきました。中には外国人による民泊のための土地家屋の売買や外国人の流入を規制すべきとの主張も一部ありました。しかし、今対策すべきは、外国人の排除ではなくて、際限なく観光客を増やせ増やせとやってきた国や京都市の観光政策の転換であり、不動産の投機的介入を放任したまちづくり政策の転換であると考えます。
京都市は、国が成長戦略に位置付けた観光立国方針をそのままに、外資系ホテルの大規模進出をはじめとした規制緩和によるホテル開発、学校跡地などの公共施設をホテル経営のために差し出してきました。2016年発表の「宿泊施設拡充・誘致方針」はこの流れに拍車をかけましたが、当時から、党市議団は「京都の景観と良さを壊」し、「歴史文化都市京都の将来に禍根を残す」として、反対してきました。
-723x1024.png)
現在の宿泊施設に関する状況はどうでしょうか。パネルを見てください。今年示された、京都観光総合調査によれば、令和6年度の観光客数は5606万人、「過去最高の平成27年5684万人とおおむね同水準」の域に達しました。2017年策定の「宿泊施設拡充・誘致方針」は、2020年度に外国人宿泊客数440万人を受け入れるためにあと1万室合計4万室の客室数が必要としていましたが、観光客総数はコロナ前と変わらない水準であるのにたいし、宿泊施設の客室数は、いまや4万室をはるかに超え6万室以上となっています。「宿泊施設拡充・誘致方針」では「市内には一戸建て・長屋建ての空き家は4万4千軒あるとされ、空き家活用の観点から、周辺地域との調和を前提に、宿泊施設として活用していく」としていますが、住宅地への宿泊施設の設置が際限なく進められたことは問題です。
東山区で「民泊反対」の貼り出しをしているお宅が10軒ほどある地域の声を聞きました。「深夜3時に路地裏でスーツケースをゴロゴロ言わせて通るのは日常茶飯事」「路地裏で裸でいるなど非常識な宿泊客もいる」「バスの定期券を持っていてもバスに乗れなくて何本も待たないといけない。歩いて帰ってくることもある」「こんなんやったら滋賀県に移住した方がマシ」「空き家ができたら不動産業者が次々入ってきて安心して暮らせない」など、怒りのお声でした。左京区や上京区でも「住宅地に民泊はいらない」の声が上がっています。また、連棟長屋の壁を隔てて民泊営業が行われているお隣の住民は、入れ替わり立ち替わりの宿泊客に心の休まる日がありません。事業者への対応にも苦慮されています。
これまで京都市は住環境の調和と言って、民泊事業者と町内会の協定書の締結、さらには観光客による京都観光モラル宣言の促進など、自助努力の対策を掲げてきましたが、観光客は入れ替わり立ち替わり、宿泊施設の事業者も変わります。住民の安心が得られる対策にはなりえていません。
住民の不満に正面から向き合い、「良質な観光と安全安心のまちづくり」に向けて、「市民が安心して暮らせ、観光客の満足も充足させる」観光政策に、抜本的に見直すべきです。そのためには、無尽蔵な観光客の誘致促進をやめ、住宅地に流入する観光客を抑制すべく、住民生活が守られる適正な宿泊施設の立地にすべきと考えます。
すなわち、「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」は廃止して、宿泊施設の増加を抑制し、観光客の総量的抑制へと転換すべきと考えますがいかがですか。具体的には、すべての宿泊施設について、住宅地の立地規制や、長屋の活用の規制を導入し、簡易宿所はすべて管理者常駐を条件とし、住宅宿泊事業は和歌山県のように隣家の同意を求めたり、住宅地0日規制を導入するなど、市民生活と調和するための条件を課すべきと考えますがいかがですか。
【答弁→岡田副市長】 京都市宿泊施設拡充・誘致方針は、量の確保ではなく質の高い宿泊政策実現を示したもの。「京都観光振興計画2025」にも継承されており、市民生活との調和につながるよう、宿泊施設の質の向上を図る。市民からの意見は「民泊通報相談窓口」を通じて調査指導に取り組んでいる。住居専用地域での民泊営業の法をこえた規制は困難であり、法の見直しを国に求める。条例による規制強化を検討する。宿泊施設の立地規制は、地域が取り組む地区計画策定に専門家を派遣するなど支援する。
6.山科区の市民の声を聞き、公共交通充実を
最後に、山科醍醐のまちづくりについて公共交通の充実を求め質問します。
ミータス山科-醍醐「みんなで創るまちPLAN」の構想が3月に発表されました。ラクトのフロア売却や東部クリーンセンター跡地売却は中止し、公共施設として整備することは、求めてきたことです。図書館や子どもの遊び場、そして公園整備が、子どもからお年寄りまで、誰もが安心して集える施設整備となるよう求めます。また、山科駅が特急はるかの発着駅となります。住民の皆さんが1600筆以上の陳情署名で山科駅北側スロープのバリアフリー化を求めてきました。山科駅の改良に際し、再度実現を要望します。
一方、山科醍醐のまちづくりの課題として、住民の方が一番に求め、努力されてきた公共交通の充実について、具体策がないことは大変不十分であり、対策を強化すべきと考えます。そもそもミータス山科醍醐のプランは外環沿線を重点化した内容となっており、地元の皆さんから不満の声も寄せられていました。山科醍醐の周辺地域も含めさらなる充実を目指すまちづくりプランとすべきであり、公共交通の充実を位置付けるべきです。
1997年地下鉄東西線の開通に伴い、山科区では市バスが撤退し、京阪バスが路線を担っています。この間続いている公共交通事業者の人手不足や赤字経営によって、山科では2020年12月以降3回も路線縮小や減便が行われています。そこで住民アンケートを実施しました。
西野山団地のバス停は、区役所へ行くバスがなく、また京都駅八条口へ行く路線がなくなり、新十条通りのバス停まで歩いて行くのが大変で困っておられます。随心院のバス停が最寄りの方は、運転免許を返納し、最大限京阪バスを利用しておられますが、「1時間に3本」が「2時間に3本」になり、山科駅、区役所、東部文化会館等に行きにくくなりました。九条山が最寄りの方は、東山方面に行くのに1日に7本しかなく、1本もない時間帯が4時間もあり、随分と不便になって困っていると言います。新奈良街道を走る大塚・小山の路線は、特に平日朝7時から10時半まで1本もないのはとても不便だと、5年前に増便を求める陳情署名を出されましたが、逆に1便減って1日7本になってしまいました。
地下鉄沿線の大通りでも、三条通の五条別れのバス停に昼間数時間バスの便がないことや、南北の外環沿線では1時間に3本あったのが、2時間に3本の半分に減らされて、おでかけに随分と制約が多くなったと言われます。高齢者の方は特に、地下鉄駅のホームまでの上り下りも大変で、最寄りで乗り降りできるバスが助かるという声を聞いて、改めてバスの重要性を認識しました。
この間続く京阪バスの減便に対して、京阪バスの経営も厳しいので仕方ないで済ませることではありません。市バスが撤退した際の全会一致の京都市会決議は「山科・醍醐地域の京阪バスの系統の編成、ダイヤの設定等については、地元住民の足の利便性を確保する観点から京阪バスとの協議に最善を尽くし、市民の要望に応えるべきである」と述べています。そうであれば、まずは、京都市として、減便で困っている山科の公共交通の実情について、市民の声を広く聞いていただきたい。さらに、その声を京阪バスに届け最善を尽くした協議を実現するよう求めます。いかがですか。
京阪バスが、市民の要望に応えられないのであれば、最終責任は京都市にあります。京都市として山科に再び市バスを走らせて、公共交通網の確保に責任を果たすべきです。いかがですか。切実な住民の願いに応えていただくよう求めて質問を終わります。
【答弁→都市計画局長】 山科醍醐地域のバス事業については地下鉄東西線開業にともない、京阪バスに一元化した。京阪バスには適宜ダイヤ維持など申し入れている。市民、京阪バス、交通局、行政が一堂に会する「山科地域公共交通会議」でも議論している。こうした議論に基づき、昨年の京阪バス減便ではできる限り生活交通を守る対応が図られた。京阪バス減便は運転士不足によりやむを得ないが、市バスも運転士不足で、路線・ダイヤ維持に苦慮している。ミータス山科-醍醐「みんなで創るまちPLAN」に掲げる、京阪バスと地下鉄の連携をすすめる。