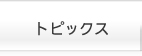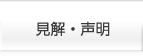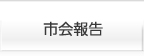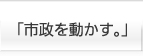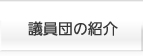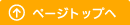10月30日、山田こうじ議員が行った2018年(H30)一般会計、国保・介護保険会計決算に対する反対討論は、下記の通りです。
日本共産党京都市会議員団は、報第1号30年度一般会計決算、報第3号国民健康保険特別会計決算、報第4号介護保険特別会計決算について認定していません。その理由を述べ討論します。
認定しない第1の理由は、大型開推進の一方で、暮らしの願いに背を向けているからです。
「京プラン」後期実施計画により、社会福祉関連経費を含む事務事業見直しで600億円の削減目標を上回るペースで、福祉・市民サービスを後退させ、赤ちゃんからお年寄りまでの暮らしに直結する予算削減、乾いたタオルを絞った行政改革により、市民生活に痛みを押しつけています。
「高すぎる国民健康保険料を引き下げてほしい」との声は切実です。京都市の国民健康保険の被保険者の5割を超える方が所得0。2,000千円以下の世帯が9割を占める状況で払いたくても払えないのが実態です。高すぎる国保料が払えない市民に対して、京都市は制裁措置として、債権の差し押さえを行っていますが、2017年度には3,222件5億90,02万6千円にものぼります。決算年度は、黒字のうち37億20,00万円を、国保基金と財政調整基金に積み立てましたが、保険料を原資とする財源を一般会計に繰り入れたことは問題です。高すぎる国民健康保険料に苦しむ加入者の負担軽減にこそ使うべきです。
京都市が加入している「近畿国民健康保険者協議会」は、公費投入を増やして国保料を引き下げることを国に要望しています。国民健康保険が協会健保等に比べて保険料が高くなるのは、世帯一人当たりにかかる「均等割」、世帯に掛る「平等割」の負担があるためです。
少子化対策にも逆行する、均等割について、京都市独自の減免を求めましたが冷たく拒否されました。また、「子育て日本一どころか」全員制の中学校給食を実施も計画もしていないのは、京都府内では亀岡市と京都市だけです。子どもの医療費の無料化では、京都府内最低水準です。待機児ゼロどころか、希望する保育所に入れずに、求職活動を中止するなど、毎年500人以上が潜在的待機児となっています。公立保育所の廃止は行わず、認可保育所の増設こそ必要です。
市民の切実な暮らしの願いには、冷たく背を向ける一方、未来への投資、国家的プロジェクトだと北陸新幹線延伸など、無駄な大型公共事業を推進しようとしているのは重大です。
第2の理由は、安倍政権による「地方創生」、「自治体戦略2040構想」をそのまま京都市に持ち込み、「民間にできることは民間に」の路線を進めてきたからです。自治体の役割である「住民福祉の増進」を根本的に覆すような事態が進行しつつあります。市長は、2007年12月の市長選挙出馬表明で「乾いたタオルを絞るような、さらなる行革も必要」と、この11年間で職員数を3,337人削減し、自治体業務の民間委託、市営保育所の廃止、区役所の税業務・衛生業務・民泊対応業務の集約などが行われ、市民の利便性が後退してきました。
これまで区役所・支所などで行ってきた戸籍や住民票などの証明書類を郵送で発行する業務を集約委託化した「証明郵送サービスセンター」において大幅な遅延が生じました。7月中旬にスタートし、一か月半後には3週間の遅れになっていました。あってはならない行政サービスの低下が起こっています。申請書類はすべてが整っているとは限りません。何の目的に使う証明か、時には、申請者に問い合わせが必要なこともあり、それまでの蓄積と専門性がある市職員が行うからこそできる仕事です。「民間にできることは民間に」と、2億円もかけて委託して、遅延を発生させ、行政サービスの低下を引きおこし、効率性も失っていることを重く受け止めるべきです。
さらに、京都市が2020年4月に、現在区役所・支所で行っている介護保険の認定給付業務を集約のうえ民間企業へ委託し、介護保険嘱託員130人を雇い止めにしようとしています。これは、介護保険制度の運営責任を民間企業に丸投げして市民サービスを後退させるとともに、介護保険制度発足時から働いてきた嘱託員を雇い止めするという、雇用主としての責任をも放棄するものであり、到底容認することはできません。
区役所職員は、門川市長が就任以来689人も削減され、今年度の分も含めれば1,000人に迫る削減が行われようとしています。その結果、昨年の台風や豪雨による災害時に設置された学区の避難所に、職員は配置できず、り災証明書の発行が遅れるなど、災害対応の脆弱さが露呈しました。災害が多発する中、消防職員を54人も削減し、消防出張所の廃止や消防隊の減隊まで行われていることも認めることはできません。
「京プラン」に基づくさらなる職員削減は撤回することを求めます。
第3の理由は、呼び込み型開発と観光インバウンド一辺倒で、京都のまちなみを壊し、地域経済を大きく落ちこませているからです。
「持続可能な都市構築プラン」「新景観政策のさらなる進化」による、高さ規制や容積率の緩和は、新景観政策に反するものです。規制緩和で地価高騰を招くことになれば、若年層が住み続けられなくなり、大型店の進出などで地元商店街が次々と姿を消し、買い物難民など、一層暮らしにくい街にならざるを得ません。
「宿泊施設拡充・誘致方針」のもと、住環境と景観破壊も深刻です。「旧御室御所」として、世界遺産にも登録されている真言宗御室派総本山仁和寺の目と鼻の先に、高級ホテルの建設が計画され、危惧する声が広がっています。仁和寺そのものがユネスコの世界遺産に登録され、「高級ホテル」予定地はバッファゾーン内にあり、世界遺産を保存する役割を担っている地域にあたります。京都市の役割として厳格に保存の姿勢に立つべきことを求めるものです。
観光消費額は年々増加していますが、地域経済に循環されていません。京都市の事業所減少率は政令市ワースト2位となり、1991年からの25年間で3分の1の事業所が消え、市内から働く場が失われています。観光インバウンド頼みの経済構造の中で、サービス業に携わる非正規雇用が拡大する中、非正規雇用率は政令市ワースト1位という現状で、勤労世帯1世帯当たり1か月収入も25%も落ち込んでいます。
京都の基幹産業である、和装産業の落ち込みはさらに深刻です。1975年のピーク時から生産量は、西陣帯はわずか6.7%、京友禅はわずか3.6%と壊滅的状況となっています。市長総括質疑でも、同僚議員が「手描き友禅の仕事を続けたかったが、この仕事では食べていけない」との友禅職人さんの声を紹介していました。工賃が下がり続け、文字通りワーキングプアというのが、伝統産業の技術を持った職人さんの実態です。こうした方への直接支援は待ったなしの状況です。伝統産業の各現場の徹底した調査と市が主体となった対策を打ち出すことが必要です。
代表質問の答弁で「地域企業、中小企業の成長支援、世界で活躍する企業の拠点進出などを背景に、京都経済は緩やかな回復基調とされている。有効求人倍率も過去最高水準、正規雇用の伸びが非正規の伸びを大きく上回っており、高い水準の雇用情勢となっている。」との認識は、こうした深刻の実態には目を向けないものです。
京都経済の活性化を図るために「経済の地域内循環」が必要としていますが、言葉ばかりで実態は、新たな価値の創造による「知恵産業」推進事業など特定のITやベンチャー、コンテンツ、先端産業、海外転換支援と一部の企業応援ばかりの産業政策です。業界全体の底上げを図るためにも、既存の中小企業や商店街、伝統産業従事者の実態調査を行い、それぞれの業界が事業として成り立つための適切な支援を強め「地域循環」で京都経済を立て直す方向への転換を求めます。
国の「地方創生」「自治体戦略2040構想」の路線を京都市政に持ち込み、呼び込み型開発や観光インバウンドを優先する一方、市民の暮らしは切り捨て、「公共サービスの産業化」で自治体を大企業の儲けの場へと差し出す市政から、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」とする、地方自治法の精神が生きる自治体へ転換する必要があることを指摘し、討論とします。
ご清聴ありがとうございました。